介護職の夜勤がなぜこれほど「きつい」と言われるのか?
介護職は高齢化が進む日本社会において必要不可欠な職種です。
その中でも「夜勤」は多くの介護士が「最もつらい」と感じる業務の一つです。実際に厚生労働省の調査によれば、離職理由の上位には「夜勤や不規則な勤務形態による体調不良」が含まれています。
夜勤は通常、夕方17時から翌朝9時までの約16時間勤務で、夜間帯は人員が最小限となるため、肉体的・精神的な負担が非常に大きいのが特徴です。
また、業務内容も多岐にわたり、安否確認・排泄介助・ナースコール対応・緊急時対応などをすべて限られた人数で行わなければなりません。
本記事では、介護職の夜勤が「なぜつらいのか」という根本的な理由を分析しながら、現場のリアルな声や具体例を交えて詳しく解説していきます。さらに、夜勤を続けるための工夫や、自分に合った働き方を見つけるためのヒントも紹介します。
1. 長時間勤務による体力的疲労
夜勤は一般的に16時間勤務であることが多く、これは通常の8時間労働の2倍にあたります。仮眠時間が設けられている施設もありますが、実際には緊急対応や業務の多さから、ゆっくり休むことができないこともあります。
- 定期的な巡回(2~3時間ごと)
- 複数人のトイレ誘導・おむつ交換
- ナースコールの頻発
- 徘徊・転倒などの緊急対応
現場の介護士の声として、「仮眠時間があるといっても、電話が鳴ればすぐに対応。気が抜けず、ぐっすり眠ることなんてできない」「夜勤明けはフラフラ。帰り道も事故を起こしそうで怖い」といった声が多く聞かれます。
特別養護老人ホームで働く30代女性介護士は「夜勤のときは一晩でおむつ交換を10人以上、コール対応20回以上。帰るころには腰が痛くて立っていられません」と話しています。
2. 生活リズムの乱れと健康への影響
夜勤の最大の課題の一つが「生活リズムの乱れ」です。人間の体は昼に活動し、夜に休息を取るように設計されています。そのため、夜勤を続けると自律神経が乱れ、様々な健康リスクが高まるのです。
- 不眠・睡眠障害
- 食欲不振、消化不良
- 頭痛や目の疲れ
- ホルモンバランスの乱れ(特に女性)
ある調査では、夜勤を継続している介護士のうち約60%が「慢性的な疲労を感じている」と回答しています。また、交代制勤務によって体が慣れにくく、免疫力が下がりやすいという報告もあります。
「夜勤明けに眠れず、翌日まで頭がボーッとする。休みの日も体調がすぐれず、家族サービスもできない状態。夜勤は年齢を重ねるほどきつくなる」との声もあります。
3. 少人数体制による業務の重さ
夜勤時は施設の人件費節約のため、多くの施設で「少人数体制」を取っています。中には「ワンオペ夜勤(1人だけで夜勤)」という非常に過酷な勤務体制も存在します。
- 職員1人で20人以上の利用者を担当
- トラブルが同時に発生した場合、対応が間に合わない
- 記録業務も夜勤者が担当することが多い
- 介護士自身が体調を崩しても代わりがいない
介護の質を保つためには、1人あたりの業務負担を適切に管理する必要がありますが、現場ではそれが困難なケースが多々あります。
4. 精神的ストレスと孤独感
夜勤は業務の量と質だけでなく、精神的にも大きな負担となります。特に孤独感や責任の重さは、介護士の精神を大きく消耗させます。
- 1人で重大な判断を下さなければならない
- 緊急時にサポートが得られない
- 他スタッフとの連携が取りづらい
- 日勤との情報共有不足による誤解や摩擦
また、夜勤者は日勤スタッフと関わる時間が短く、コミュニケーション不足から「理解されていない」「孤立している」と感じることもあります。
5. 夜勤を乗り越えるための工夫と対策
夜勤が過酷であることは否定できませんが、工夫次第でその負担を軽減することも可能です。ここでは現場で実際に効果があったとされる夜勤の工夫や対策をご紹介します。
- 仮眠を最大限活用する:15~30分の「パワーナップ」が脳の疲労を回復させる。
- 夜勤前の食事を見直す:脂っこいものや糖分を控え、消化の良い食事にする。
- カフェインを摂るタイミングを工夫:夜勤序盤はOKだが、明け方に飲むと睡眠に悪影響。
- 仮眠室の照明・温度調整:アイマスクや耳栓、冷暖房を使って快適な環境を整える。
- 勤務後のルーティンを作る:帰宅後に軽いストレッチやシャワーでリラックス。
また、同僚との連携も非常に重要です。申し送りでの情報共有や、互いの体調を気遣う文化がある職場は、夜勤のストレスを軽減できます。信頼関係があるチームでは、緊急時も冷静に連携できるため、精神的な安心感も生まれます。
ある介護施設では、夜勤前後に「5分のリラックスタイム」を設けており、コーヒーや軽食を囲んでの交流が職員の心の支えになっています。結果、夜勤者の離職率が半減したという報告もあります。
6. 介護職で夜勤を続けるべきか?判断のポイント
夜勤が辛いと感じたとき、「このまま続けてよいのか」「転職した方がいいのか」と悩む方も多いでしょう。以下の視点から、自分に合う働き方を再検討することをおすすめします。
- 自分の年齢や体力とのバランス:40代以降は夜勤がより身体に堪える。
- 家庭環境や生活スタイル:子育てや介護など、夜勤が難しい時期もある。
- 夜勤手当による収入とのトレードオフ:収入アップが目的か、生活の安定か。
- 精神面の負担:うつや不安などが強い場合は、日勤への切り替えも視野に。
また、現在では夜勤のない介護職も増えています。以下のような選択肢も検討してみましょう。
- デイサービス(夜勤なし)
- 訪問介護(早朝や夜間勤務を避ける調整も可能)
- 介護事務や相談員などの職種転換
介護職への転職を考えているなら、信頼できるサポートがあるサイトを選びましょう。
✔ 「今の職場に不安がある」
✔ 「未経験から介護職にチャレンジしたい」
そんな方は、まずはこちらから無料で求人をチェックしてみてください!
👉ケアハンティング
夜勤はつらいが、対処と選択肢で変わる未来
介護職の夜勤は、体力的にも精神的にも非常に厳しい業務です。しかし、職場環境やチーム体制、自分自身の工夫によって、その負担を軽減することは可能です。
夜勤が自分に合わないと感じたら、それは甘えではなく「自分を守る大切な判断」です。キャリアの見直しや職場の変更も含めて、柔軟な選択ができる時代になっています。
最後に一つ大切なことは、「自分の健康と生活を守ること」。無理をして続けることが最善ではありません。夜勤のつらさを理解し、自分にとって最適な働き方を見つけていきましょう。
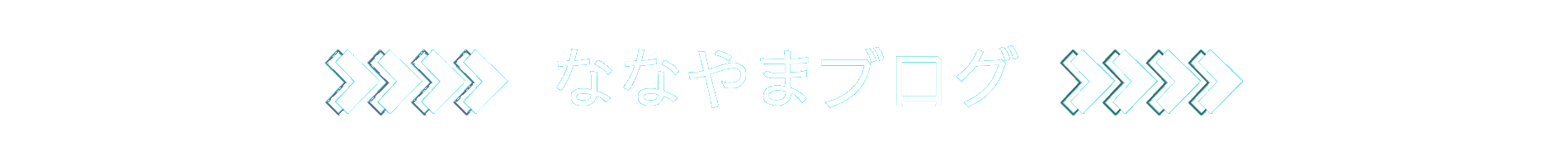

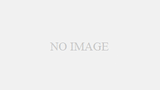
コメント